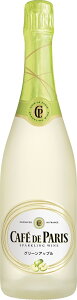
カフェ・ド・パリ・ブラン・ド・フルーツ グリーンアップル750ML やや甘口フランス生まれのスパークリングワイン、「カフェ・ド・パリ」。豊富なバリエーションのフルーツフレーバーが選ぶ楽しさを提供します!シャルマ方式で造られるフランス産スパークリングワインに、フルーツなどから抽出したナチュラルフレーバーを加えました。アルコール度数は7%前後と低めに抑え、やさしい泡立ちと上品な甘さのスパークリングワインです。 「カフェ・ド・パリ ブラン・ド・フルーツ グリーンアップル」は、グリーンアップルの爽やかなでフレッシュな香りと味わいが特徴です。
価格:1,304円

【気になる商品】 Man&Wood(マンアンドウッド)の「天然木スマートリング2」は、人気の天然木を使用したおしゃれなスマートリングです。■ 最高の香りを最高の木に素材には高級家具、楽器、インテリアアクセサリに使われる最高級の天然木に最先端ナノ技術を通してほのかな香りを実現しました。香りは、高級香水によく使われる沈香です。■ おしゃれな天然木天然木を使用したおしゃれなデザインのスマートリングです。薄く仕上がっているので、端末に付けた時も軽く、邪魔になりません。人気のMan&Wood 天然木ケースとお揃いで使用も可能です。自分だけのウッドケースをお楽しみいただけます。■ 自由に360度回転、180度角度調節リング部分は、自由に360度回転、また180度角度調節できるので、自分の好きな角度で指にはめたりスタンドにしたりできます。■ 落下防止ホールドリングは指をリングにはめて使用することで、スマホが落下することを防ぎます。■ 便利なスタンド機能リング部分を角度をつけて固定することによって、端末のスタンドとしても使用することができます。動画の視聴などに便利です。■ 付け外しは簡単な粘着シート裏面の粘着シートは、付け外しが可能です。水洗いして乾かすことにより吸着力が回復し、何度でも使用できます。■ 車載、壁掛けホルダー付き専用車載、壁掛けホルダーが付属で付いてるので車内やデスク周りでもお好きな角度でご使用いただけます。[仕様情報]対応機種 : 各種スマートフォンおよびタブレットタイプ : スマホリング/スマホホルダー素材 : 天然木、ポリカーボネート、金属【注意事項】※ご注意ください・ スタンド機能以外の場合はスマートフォンを手に持った状態でリングに指を通して使用するようお願いいたします。・ スマートフォンの重量や形状、材質、特殊コーティング処理によって張り付け強度に差が生じます。 張り付きにくい場合は必ずジェルパッドに対応できるハードケース(PC)などを付けてからご使用くださいますようお願いいたします。(※iPhone X、iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plusの一部カラー(マットブラック、ジェットブラック)など)・ シリコンケース等のソフトケース、接着面に汚れや傷、凹凸、または湾曲がある製品にはご使用頂けませんのでご注意下さい。・ 皮革、布、シリコン等の素材には使用頂けません。・ 本製品は装着した機器の落下を防ぐものではありません。・ 本製品を使用して発生したトラブル・事故・落下による破損等につきましては一切の責任を負いかねます。・ 本製品は、改良・改善のため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので予めご注意ください。 [メーカー]マンアンドウッド Man & Wood 型番 JAN Ebony I13058 4589753020580 Carbalho I13059 4589753020597 Pecan I13060 4589753020603 Koala I13061 4589753020610 Jupiter I13062 4589753020627 Browny Check I13063 4589753020634 Zebrano I13064 4589753020641 Madrona I13065 4589753020658 [対応] スマートフォン[性能] スタンド機能[材質] 木製[色] エボニー[色] カルヴァリョ[色] コアラ[色] ジュピター[色] ゼブラノ[色] ピーカン[色] ブラウニーチェック[色] ブラウン[色] マドロナMan & Wood 天然木スマートリング2 マンアンドウッド注目ポイント注目ポイント注目ポイント注目ポイント注目ポイント注目ポイントカラーバリエーション注目ポイント
価格:1,069円

価格:3,758円
Appleの携帯だけの激安、お買い得、セール情報などをお届け!
今回は演奏会の感想ではなく、別の話題を。
以前、「もしもタイムマシンがあったなら行ってみたい演奏会」シリーズとして、行ってみたいフルトヴェングラーのコンサートをつらつら書いていたことがあった。
今回、久々にその続きを書いてみたい。
フルトヴェングラーの次ということで、今度は当時彼と並び称された名指揮者、アルトゥーロ・トスカニーニの演奏会から選んでいくこととしたい。
なお、トスカニーニの演奏会記録についてはを参照させていただいた。
20世紀前半において人気を二分した指揮者であるフルトヴェングラーとトスカニーニは、音楽性もまた対照的とされることが多い。
トスカニーニは
「楽譜に忠実な解釈で、イン・テンポ(テンポを一定に保つ)による躍動的な演奏だが、やや一本調子で柔軟性に欠けるきらいがある」
というように評され、一方フルトヴェングラーは
「楽譜の表記にこだわらない解釈で、テンポを自由に揺らすロマン的な演奏だが、やや重々しすぎ推進力に欠けるきらいがある」
といったようなことをよく言われるように思う。
確かに、こうしたことは、一面では正しい。
ただ、こうした面だけでは、彼らの演奏の特徴を捉えることができないように思う。
トスカニーニは、実はフルトヴェングラーよりも20歳近く年上である、ということに留意する必要がある。
トスカニーニと同年代の指揮者は、グスタフ・マーラーやフランツ・シャルクらである。
マーラーやシャルクは、私たちの想像以上に楽譜に大きく手を加えていた(改変していた)ようであり、トスカニーニは、そのようなことをすべきでないと主張した最初期の人であった。
それから少し後の世代のフルトヴェングラーやクレンペラーの頃には、トスカニーニのように楽譜にあまり手を加えないやり方がすでに主流になっていた。
実際、残された録音を聴き比べてみると、楽譜への忠実度は「楽譜至上主義者」トスカニーニと、「自由な解釈者」フルトヴェングラーとで、それほど大きく変わらない(レッテルだけ見ると、あたかも正反対の主義を持つかのようだが)。
また、彼ら2人の世代の違いは、残された録音にも大きく影響している。
フルトヴェングラーの生涯を10年ごとに大まかに分類すると
?0歳代(1890年頃) 子供時代
?10歳代(1900年頃) 修業時代
?20歳代(1910年頃) リューベック管弦楽団
?30歳代(1920年頃) マンハイム歌劇場
?40歳代(1930年頃) ベルリン・フィル(戦前)、ウィーン・フィル
?50歳代(1940年頃) ベルリン・フィル(戦中)
?60歳代(1950年頃) ベルリン・フィル(戦後)
となり、このうち私たちが録音で聴けるのは???である。
それに対し、トスカニーニの場合は
①0歳代(1870年頃) 子供時代
②10歳代(1880年頃) 修業時代
③20歳代(1890年頃) トリノ・レージョ劇場
④30歳代(1900年頃) ミラノ・スカラ座(一次大戦前)
⑤40歳代(1910年頃) ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場
⑥50歳代(1920年頃) ミラノ・スカラ座(戦間期)
⑦60歳代(1930年頃) ニューヨーク・フィル
⑧70歳代(1940年頃) NBC響(戦中)
⑨80歳代(1950年頃) NBC響(戦後)
となり、このうち録音が残されているのは⑦⑧⑨である(⑥も残されてはいるが、ごくわずかであり、またアコースティック録音のため音質があまりに貧弱)。
つまり、フルトヴェングラーについては、彼の主要な活動時期の演奏の多くを聴くことができるのに対し、トスカニーニのほうは、彼の人生においてきわめて重要な時期である④⑤⑥あたりの演奏を私たちは聴くことができないのである。
録音が残されていない以上、トスカニーニの演奏について、その全貌が明らかになることは残念ながら今後もないだろう。
とはいえ、私たちには、トスカニーニの⑦の時期の録音が残されている。
録音数が多いのは圧倒的に⑨の時期だが、⑦の時期の演奏には、⑨の時期のような四角四面なところがあまりなく、しなやかさがあるように思う。
一方、フルトヴェングラーのほうは、?の後半期の録音が多いためそのイメージが付きやすいけれど、??や?の前半期の演奏は、?の後半期ほど重々しくなく、適度な推進力を有している。
そんな2人の壮年期の演奏は、実は驚くほどよく似ている(もちろん、違いもあるのだけれど)。
また、この2人がよく対比された背景には、地理的な問題もありそうである。
19世紀後半における、ハンス・フォン・ビューロー(ドイツ) vs ハンス・リヒター(オーストリア)。
また、19世紀末~20世紀初頭における、アルトゥール・ニキシュ(ドイツ) vs グスタフ・マーラー[後にフェーリクス・ヴァインガルトナー](オーストリア)。
こういった各時代での名指揮者の対比には常に地理的な要因があったが、20世紀前半にアメリカの躍進とともにこれが世界規模に広がり、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(ヨーロッパ) vs アルトゥーロ・トスカニーニ(アメリカ)という構図になったのかもしれない。
20世紀後半には、この対比はヘルベルト・フォン・カラヤン(ヨーロッパ) vs レナード・バーンスタイン(アメリカ)として受け継がれた、といったところか。
なお、21世紀におけるこの種の対比については、私はまだ知らない。
ビューローやマーラーの演奏はいざ知らず、フルトヴェングラーやトスカニーニに共通する点はというと、おそらくベートーヴェンを得意とする「英雄的な」演奏様式を持つことではないだろうか。
当時のアメリカにはワルターもクレンペラーもいたにもかかわらず、専らトスカニーニがフルトヴェングラーと並び称されたのには、そういう理由があるように思う。
そして、彼らの後に続くカラヤンやバーンスタインの音楽も、同様に「英雄的な」スタイルを持っている。
こうしたスタイルを持つ指揮者は、それぞれの地域の「代表的指揮者」としての扱いを受けやすいのだろう。
前置きが長くなったが、私はトスカニーニの最盛期だった可能性の高い④~⑦あたりの時期を中心に、行ってみたい演奏会を選んでいきたい。
まずはフルトヴェングラーのときと同じく、ベートーヴェンの交響曲第5番から始める。
探してみると、下記の演奏会があった。
1926年10月7日、ミラノ
指揮:トスカニーニ
管弦楽:ミラノ・スカラ座管弦楽団
プログラム
Beethoven: Symphony No.1
Beethoven: Symphony No.2
Beethoven: Symphony No.5
翌年のベートーヴェン没後100年を記念しての交響曲全曲ツィクルスの第1日である。
トスカニーニ60歳前の、脂の乗りきった時期。
いったいどのようなツィクルスだったのか、想像するだにすさまじい。
ただしタイムマシンはまだないし、またこの演奏会のライヴ録音も残されていないので、代わりに下記の録音を聴いた。
●ベートーヴェン:交響曲第1番 トスカニーニ指揮NBC響 1951年12月21日ニューヨーク・ライヴ盤(/)
●ベートーヴェン:交響曲第2番 トスカニーニ指揮NBC響 1949年11月7、9日、1951年10月5日ニューヨーク・ライヴ盤(/)
●ベートーヴェン:交響曲第5番 トスカニーニ指揮ニューヨーク・フィル 1933年4月9日ニューヨーク・ライヴ盤()
第1、2番は、全集中のもの。
第5番については、全集に含まれる1952年盤ももちろん素晴らしいのだが、少し急いでいるような印象を受けなくもなく、テンポ設定にもう少し柔軟性が欲しい。
それに比べ、壮年期に近い上記1933年盤はより落ち着いたテンポになっており、また伸縮自在でしなやか、ロマン的でさえある。
低弦も豊かに鳴らされ迫力満点、同時期のフルトヴェングラーの同曲演奏によく似た名演となっている。
これぞ、トスカニーニ本来のスタイルなのではないだろうか。
↑ ブログランキングに参加しています。もしよろしければ、クリックお願いいたします。
Appleの置かれている状況をもう少し理解してもらいたい
英語コーチ&私設マネージャーのMinezです。
冠詞シリーズ(お、いつの間にかシリーズ化してきたw)
のココまでです。
今日はApplesの感覚を捉えます。
名詞の複数系はざっくり言うと、
Ctrl+A=全選択のイメージ。
つまり
赤いりんご
青いりんご
大きいりんご
小さいりんご
りんごと名のつくモノなら何でもアリ!
この感覚ですね!
つまり・・・
I like Apples.というと、
りんごというモノならどれを取っても好き?
I like dogs.
犬というモノならセントバーナードからチワワまで、
毛の短いのから長いのも、好き?
わかりやすいですよね。
この感覚!
「アジアで通用する英語力を身に付ける」7つのステップについて解説!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
- [ ]
Appleを配信中
 Apple 関連ツイート
Apple 関連ツイート
ミオヤマザキのMVがApple Music等ビデオ配信ストア解禁?さらに最新アルバムun-speakable全曲のMVを配信開始。映像も音源も全曲圧倒的。必見。
??今すぐ見る
https://t.co/…
